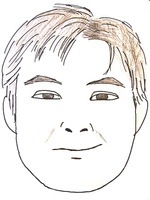2019年05月11日
新たなトリガーレスの形
釣具店に勤務している弟に、欲しかったルアーの配達を依頼。
届いたルアーとはべつに、3台のリールと1本のロッドが?
リールのメンテナンスとロッドの改造を依頼されたw
リールは、IOSのオイルやグリスでメンテナンスをして、いい感じに仕上がった。
ロッドの方は、トリガーレスへの改造依頼。
ロッドは、シマノのエクスプライド。
シマノのロッドは、計量化のため、グリップの内部が空洞になっており、トリガーを完全に取り除くと、穴が開いてしまう・・・
そこで、トリガーを一部残した形で、フェンウィックのトリガーレスを参考にしながら、加工。
15分ほどの加工で、出来上がったのがこちら。

自分のロッドは、完全なトリガーレスなのだが、この一部残した形のトリガーレスは、意外なほど持ちやすい!
今後は、自分のロッドもこの形のトリガーレスを採用する予定。
なお、DEN工房では、このようなロッドの加工やリールのメンテナンスは、受け付けておりませんので、ご了承くださいw
届いたルアーとはべつに、3台のリールと1本のロッドが?
リールのメンテナンスとロッドの改造を依頼されたw
リールは、IOSのオイルやグリスでメンテナンスをして、いい感じに仕上がった。
ロッドの方は、トリガーレスへの改造依頼。
ロッドは、シマノのエクスプライド。
シマノのロッドは、計量化のため、グリップの内部が空洞になっており、トリガーを完全に取り除くと、穴が開いてしまう・・・
そこで、トリガーを一部残した形で、フェンウィックのトリガーレスを参考にしながら、加工。
15分ほどの加工で、出来上がったのがこちら。

自分のロッドは、完全なトリガーレスなのだが、この一部残した形のトリガーレスは、意外なほど持ちやすい!
今後は、自分のロッドもこの形のトリガーレスを採用する予定。
なお、DEN工房では、このようなロッドの加工やリールのメンテナンスは、受け付けておりませんので、ご了承くださいw
2019年03月15日
ワイヤーを曲げてディープトレーサーを試作することに
フィッシングショーや釣り雑誌で、今シーズンの新製品をチェックした中で、気になったのがディープトレーサー。

ビッグベイトをディープに送り込むためのアイテムらしい。
これでクランクベイトをディープに送り込めたらおもしろそうだと、早速スピナーベイトを改造して製作。

先日の兄弟船での釣行で、キャストしてみたものの、最初の3投で3回ワイヤーにフックが絡むトラブル発生・・・
そこで、ワイヤーを開いて、クランクベイトとシンカーの部分を離してみたら、その後はトラブルレスに。

スモールクランクならこれでいけそうだが、レギュラーサイズのクランクベイトだと、全体的にもう少し大きいほうがよさそうだ。
そこで、帰宅後に早速ワイヤーを曲げて自作開始。
本家を参考にして、ワイヤーも少し曲げてみることに。

スピナーベイトを改造したモデルより、一回り大きく作ってみた。
後は、実際に釣り場でキャストしてみて、また調整してみる予定。

スピナーベイトを改造したモデルでは、ウエイトの調整も出来なかったため、次はまたいろいろ試せそうです!

ビッグベイトをディープに送り込むためのアイテムらしい。
これでクランクベイトをディープに送り込めたらおもしろそうだと、早速スピナーベイトを改造して製作。

先日の兄弟船での釣行で、キャストしてみたものの、最初の3投で3回ワイヤーにフックが絡むトラブル発生・・・
そこで、ワイヤーを開いて、クランクベイトとシンカーの部分を離してみたら、その後はトラブルレスに。

スモールクランクならこれでいけそうだが、レギュラーサイズのクランクベイトだと、全体的にもう少し大きいほうがよさそうだ。
そこで、帰宅後に早速ワイヤーを曲げて自作開始。
本家を参考にして、ワイヤーも少し曲げてみることに。

スピナーベイトを改造したモデルより、一回り大きく作ってみた。
後は、実際に釣り場でキャストしてみて、また調整してみる予定。

スピナーベイトを改造したモデルでは、ウエイトの調整も出来なかったため、次はまたいろいろ試せそうです!
2019年03月11日
スピナーベイトでディープトレーサーを試作
今回の新製品の中で、一つ気になったアイテムが、リュウギのディープトレーサー。

《画像は、RYUGIのホームページより》
ビッグベイトをディープに送り込みながら、しかも根がかり減少という、単純な仕組みながら、素晴らしいアイデア!
とはいえ、ビッグベイトをほとんど使用しない自分には、不要なアイテム。
そう思っていたのだが、手持ちのクランクベイトを同じように使えることに気付き、早速試作することに。
当初はワイヤーから曲げて作るつもりだったが、とりあえず試作なので、あるものを活用することに。
ディープトレーサーと形の似ている、スピナーベイトを活用してとりあえずやってみる。
まずは、手持ちのスピナーベイトを準備。

フックをニッパーでカット。
スカートとブレードも外す。
そして、ブレードの部分にスナップを取り付けて完成。

実際に使用するときは、スナップにクランクベイトを取り付ける。
これで、ディープにスモールクランクやシャロークランクを送り込める予定。

手持ちのルアーを増やすことなく、レンジを変えることができるので、上手くいけば持っていくルアーを減らすことに役立つかも・・・
また次回釣行の楽しみが一つ増えましたw

《画像は、RYUGIのホームページより》
ビッグベイトをディープに送り込みながら、しかも根がかり減少という、単純な仕組みながら、素晴らしいアイデア!
とはいえ、ビッグベイトをほとんど使用しない自分には、不要なアイテム。
そう思っていたのだが、手持ちのクランクベイトを同じように使えることに気付き、早速試作することに。
当初はワイヤーから曲げて作るつもりだったが、とりあえず試作なので、あるものを活用することに。
ディープトレーサーと形の似ている、スピナーベイトを活用してとりあえずやってみる。
まずは、手持ちのスピナーベイトを準備。

フックをニッパーでカット。
スカートとブレードも外す。
そして、ブレードの部分にスナップを取り付けて完成。

実際に使用するときは、スナップにクランクベイトを取り付ける。
これで、ディープにスモールクランクやシャロークランクを送り込める予定。

手持ちのルアーを増やすことなく、レンジを変えることができるので、上手くいけば持っていくルアーを減らすことに役立つかも・・・
また次回釣行の楽しみが一つ増えましたw
2018年11月23日
お気に入りのカラーにペイントしてみました
ねらったアクションがなかなか出ず、手が止まっていたハンドメイドクランク。
ウエイトやリップであれこれ調整してみたものの、結局ねらったアクションが出ず・・・
ウエイトやリップをちょっといじったぐらいでは、自分のねらっているアクションを出すことができないこと、そしてボディ形状そのものの見直しが必要なことはわかったものの、そこで手が止まっていた。
でも、ふと思い立って、再始動。
ねらっていたアクションに近かった初期型のモデルと、最近のモデルを比べてみたら、ボディ形状が若干変わっていた!
と言うことは、初期型のモデルをさらにいじれば、ねらったアクションが出るのでは?
そう思って、従来のモデルより若干スリムなモデルの作成開始!

試しに2つだけ作成してみると、従来モデルよりずいぶんスリムに!

コーティングをすませ、リップも取り付け完了。

先日の釣行で、スイムテストを行ったところ、今まで作成した中で、自分のねらっているアクションに一番近い!
家族の体調不良ため、釣行できなかった週末の時間を使って、ペイント作業。

久しぶりのペイント作業は、すっかり腕がなまってたw
それでも、やっているうちに勘を取り戻し、何とかペイント作業も終了。

2個しかないので、一番お気に入りのグリーンバックシルバーと、ブルーギルカラーに塗ってみた。
久しぶりなので、今ひとつ納得のいかない仕上がり・・・
それでも、未塗装の状態よりは、気持ちを入れてキャストできそうだ。
あとは、このクランクベイトで釣るだけですが、それがなかなか厳しい時期になりましたねw
ウエイトやリップであれこれ調整してみたものの、結局ねらったアクションが出ず・・・
ウエイトやリップをちょっといじったぐらいでは、自分のねらっているアクションを出すことができないこと、そしてボディ形状そのものの見直しが必要なことはわかったものの、そこで手が止まっていた。
でも、ふと思い立って、再始動。
ねらっていたアクションに近かった初期型のモデルと、最近のモデルを比べてみたら、ボディ形状が若干変わっていた!
と言うことは、初期型のモデルをさらにいじれば、ねらったアクションが出るのでは?
そう思って、従来のモデルより若干スリムなモデルの作成開始!

試しに2つだけ作成してみると、従来モデルよりずいぶんスリムに!

コーティングをすませ、リップも取り付け完了。

先日の釣行で、スイムテストを行ったところ、今まで作成した中で、自分のねらっているアクションに一番近い!
家族の体調不良ため、釣行できなかった週末の時間を使って、ペイント作業。

久しぶりのペイント作業は、すっかり腕がなまってたw
それでも、やっているうちに勘を取り戻し、何とかペイント作業も終了。

2個しかないので、一番お気に入りのグリーンバックシルバーと、ブルーギルカラーに塗ってみた。
久しぶりなので、今ひとつ納得のいかない仕上がり・・・
それでも、未塗装の状態よりは、気持ちを入れてキャストできそうだ。
あとは、このクランクベイトで釣るだけですが、それがなかなか厳しい時期になりましたねw
2018年10月24日
フラットサイドクランク制作 再始動
一時期、毎晩のように作業していたハンドメイドクランク。
気がつけば、かなり数を作成。
狙ったアクションを出すために、リップやウエイトなど、ちょっとずつ条件を変えて作ってみたものの、結局狙ったアクションが出せず・・・

いろいろやった結果、ウエイトやリップを多少いじったぐらいでは、根本的な解決にならないことが分かった。
やりきった感があり、しばらく放置・・・
でも、ふと思い立って、再始動。
狙いのアクションを出すためには、、ボディ形状に手を加える必要がありそうだ。
今まで作成したフラットサイドクランクの中では、初期に作成していたモデルが、一番いい感じのアクションが出ている。
そこで、最近のモデルとどjこが違うのか比較。
すると、ボディ形状が若干スリムなことが判明!
どうやら、作り続けているうちに、若干だがファットになってしまっていたようだ・・・
そこで、初期モデルより若干スリム化して、アクションを見てみることに。
今までの型を元に、新たな型を作成。

最近作成していたモデルより、かなりスリムな形状にしてみた。
初期のモデルより、若干スリムな仕上がり具合。

時間をかけて、のんびり作ればいいや・・・と思って再始動したはずなのに、結果が早く知りたくて、一気に作業が進むw
再始動の翌日には、コーティング作業開始のハイスピード!

金曜日の夜には、リップを取り付けられるように、1日2回のペースで、合計5回のコーティング。
予定では、次の土曜日にはスイムテストができる予定!
こういう作業をすると、自分のせっかちさがよく分かりますねw
気がつけば、かなり数を作成。
狙ったアクションを出すために、リップやウエイトなど、ちょっとずつ条件を変えて作ってみたものの、結局狙ったアクションが出せず・・・

いろいろやった結果、ウエイトやリップを多少いじったぐらいでは、根本的な解決にならないことが分かった。
やりきった感があり、しばらく放置・・・
でも、ふと思い立って、再始動。
狙いのアクションを出すためには、、ボディ形状に手を加える必要がありそうだ。
今まで作成したフラットサイドクランクの中では、初期に作成していたモデルが、一番いい感じのアクションが出ている。
そこで、最近のモデルとどjこが違うのか比較。
すると、ボディ形状が若干スリムなことが判明!
どうやら、作り続けているうちに、若干だがファットになってしまっていたようだ・・・
そこで、初期モデルより若干スリム化して、アクションを見てみることに。
今までの型を元に、新たな型を作成。

最近作成していたモデルより、かなりスリムな形状にしてみた。
初期のモデルより、若干スリムな仕上がり具合。

時間をかけて、のんびり作ればいいや・・・と思って再始動したはずなのに、結果が早く知りたくて、一気に作業が進むw
再始動の翌日には、コーティング作業開始のハイスピード!

金曜日の夜には、リップを取り付けられるように、1日2回のペースで、合計5回のコーティング。
予定では、次の土曜日にはスイムテストができる予定!
こういう作業をすると、自分のせっかちさがよく分かりますねw
2018年03月03日
スイムテスト
仕事が早く終わった日の夕方、近所の川でクランクベイトのスイムテスト。
調整することを前提に、リップを少し大きめに作ってあるので、切ったり削ったりして、好みのアクションに調整していく。
これまでの経験から、リップの形状を多少いじったくらいでは、アクションは大きく変わらない。
切ったり削ったりすることで、ちょっとだけアクションをおとなしくする程度。
ラインアイを柔らかい真鍮で作っているので、ラインアイを上げたり下げたりすることができ、アクション調整をすることができる。
ただし、これも微調整程度しかできず、アクションそのものの質を変えることはできない。
ロールとウォブルのバランスを調整するために、リップの取り付け角度を変えたものをいくつか作り、実際に泳がせてチェック。
そして、気に入ったものだけが塗装作業へと進むことになる。

結構たくさん作っているのだけれど、本当に気に入ったものはなかなかできない・・・
でも、狙ったアクションに近づけるために、何をどうすればいいのか、ちょっと解明できてきた!
結局のところ、ちょっとずつ何かを変えながら、数を作るしかないですね。
調整することを前提に、リップを少し大きめに作ってあるので、切ったり削ったりして、好みのアクションに調整していく。
これまでの経験から、リップの形状を多少いじったくらいでは、アクションは大きく変わらない。
切ったり削ったりすることで、ちょっとだけアクションをおとなしくする程度。
ラインアイを柔らかい真鍮で作っているので、ラインアイを上げたり下げたりすることができ、アクション調整をすることができる。
ただし、これも微調整程度しかできず、アクションそのものの質を変えることはできない。
ロールとウォブルのバランスを調整するために、リップの取り付け角度を変えたものをいくつか作り、実際に泳がせてチェック。
そして、気に入ったものだけが塗装作業へと進むことになる。

結構たくさん作っているのだけれど、本当に気に入ったものはなかなかできない・・・
でも、狙ったアクションに近づけるために、何をどうすればいいのか、ちょっと解明できてきた!
結局のところ、ちょっとずつ何かを変えながら、数を作るしかないですね。
2018年02月25日
フラットサイドクランク作成 その9
フラットサイドクランク作成も、いよいよ大詰め。
コーティングが終わったルアーに、リップを取り付けるための切り目を入れる。
以前は、手引きのノコギリでやっていたのだが、最近は電動糸ノコを使用している。

あとは、作っておいたリップを差し込み、角度などを確認。
そして、接着剤をつけて差し込み直して、とりあえす作業終了。

ここからは、実際にフィールドで泳がせてみて、まっすぐ泳ぐように調整したり、リップの形を成形し直したりといった作業を行うことに。
そして、塗装作業、コーティング作業を経て、完成となる。
実は、この週末に近所の川でスイムテストを行ってきたのだが、ヒノキで作ったモデルは、思ったようなアクションが出せておらず、いろいろ調整した結果、ウエイト不足であることが判明。
現在のウエイトの横に穴を開け、ネコリグで使用するタングステンのネイルシンカーを追加して、アクションの調整を行う予定。

スギで作成したモデルは、非常にいい感じのアクションが出ていたので、こちらは塗装作業へ移れそうだ。
同じ形、同じウエイトで作成しても、比重の違うスギとヒノキでは、アクションが全然違っている。
どちらがいいのかは、バスに聞いてみないと分からないのだが、スギで作ったモデルの方が自分好みのアクションに仕上がることが多い。
ただ、ヒノキにはヒノキの良さがあるので、もう少し試行錯誤をしてみる予定。
本格的なシーズンインに間に合うように、頑張りますw
コーティングが終わったルアーに、リップを取り付けるための切り目を入れる。
以前は、手引きのノコギリでやっていたのだが、最近は電動糸ノコを使用している。

あとは、作っておいたリップを差し込み、角度などを確認。
そして、接着剤をつけて差し込み直して、とりあえす作業終了。

ここからは、実際にフィールドで泳がせてみて、まっすぐ泳ぐように調整したり、リップの形を成形し直したりといった作業を行うことに。
そして、塗装作業、コーティング作業を経て、完成となる。
実は、この週末に近所の川でスイムテストを行ってきたのだが、ヒノキで作ったモデルは、思ったようなアクションが出せておらず、いろいろ調整した結果、ウエイト不足であることが判明。
現在のウエイトの横に穴を開け、ネコリグで使用するタングステンのネイルシンカーを追加して、アクションの調整を行う予定。

スギで作成したモデルは、非常にいい感じのアクションが出ていたので、こちらは塗装作業へ移れそうだ。
同じ形、同じウエイトで作成しても、比重の違うスギとヒノキでは、アクションが全然違っている。
どちらがいいのかは、バスに聞いてみないと分からないのだが、スギで作ったモデルの方が自分好みのアクションに仕上がることが多い。
ただ、ヒノキにはヒノキの良さがあるので、もう少し試行錯誤をしてみる予定。
本格的なシーズンインに間に合うように、頑張りますw
2018年02月18日
フラットサイドクランク作成 その8
1日1回のコーティング作業を進めつつ、リップの制作へ。
フラットサイドクランクのリップは、現在、0.8mmのサーキットボードを使用。
特にこだわりは無いのだが、できるだけ分厚い方が丈夫でいいだろうと思いつつ、これ以上厚いと加工が大変なため、この厚みに落ち着いた。
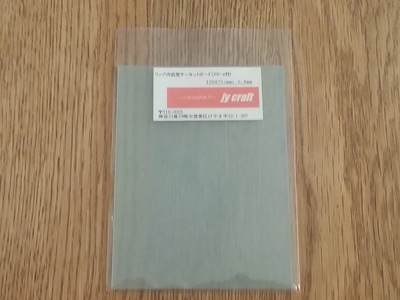
これに油性マジックで型を写し取り、金切りバサミでカット。
少し大きめにカットするのがコツ。

あとは、ヤスリで削って、成形作業終了。

コーティング作業は、しばらくかかるので、リップができた今は作業停止状態。
でも、その期間を利用して、新たなモデルを作ったりと、やりたいことがいっぱいですw

フラットサイドクランクのリップは、現在、0.8mmのサーキットボードを使用。
特にこだわりは無いのだが、できるだけ分厚い方が丈夫でいいだろうと思いつつ、これ以上厚いと加工が大変なため、この厚みに落ち着いた。
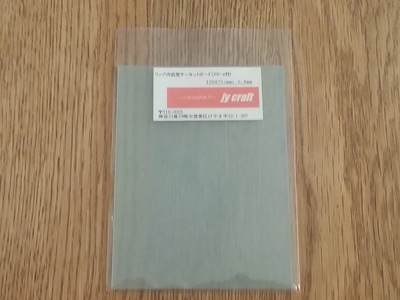
これに油性マジックで型を写し取り、金切りバサミでカット。
少し大きめにカットするのがコツ。

あとは、ヤスリで削って、成形作業終了。

コーティング作業は、しばらくかかるので、リップができた今は作業停止状態。
でも、その期間を利用して、新たなモデルを作ったりと、やりたいことがいっぱいですw

2018年02月13日
フラットサイドクランク作成 その7
せっかくの三連休も、最終日は雪のため、釣行断念・・・
でも、その分、クランクベイト作りに時間が使えるから、それはそれでいいのだけれどw
コーティング作業に入る前に、削る作業行程の見直し。
ナイフで行っていた部分をサンドペーパーで仕上げるのは、きれいに仕上がるもののかなり時間がかかる。
しかも、五十肩へのダメージも大きいw

そこで荒削りの部分は、サンダーを使って見ることに。
ちょっとコツがいるものの、明らかに楽々!
仕上げはサンドペーパーで。
これで更に作業効率がアップです。

さて、パーツの取り付けが終わった分を、コーティング。
セルロースセメントにドブ漬けして、乾燥させる作業を繰り返す。

乾燥スペースの都合で、6個ずつしか作れないのだが、これぐらいの少数が、丁寧に作業をする限界かも・・・
次は、コーティング作業中にリップの作成です。
でも、その分、クランクベイト作りに時間が使えるから、それはそれでいいのだけれどw
コーティング作業に入る前に、削る作業行程の見直し。
ナイフで行っていた部分をサンドペーパーで仕上げるのは、きれいに仕上がるもののかなり時間がかかる。
しかも、五十肩へのダメージも大きいw

そこで荒削りの部分は、サンダーを使って見ることに。
ちょっとコツがいるものの、明らかに楽々!
仕上げはサンドペーパーで。
これで更に作業効率がアップです。

さて、パーツの取り付けが終わった分を、コーティング。
セルロースセメントにドブ漬けして、乾燥させる作業を繰り返す。

乾燥スペースの都合で、6個ずつしか作れないのだが、これぐらいの少数が、丁寧に作業をする限界かも・・・
次は、コーティング作業中にリップの作成です。
2018年02月12日
フラットサイドクランク作成 その6
だんだん形になってきた、ハンドメイドクランク。
久しぶりにやっていると、やり方を忘れているところもあって、思い出しつつ、改善しつつやってます。
作業の方は、一通りの成形が終わり、次はパーツの取り付け。
ラインアイ、フックアイを取り付けるための穴を開ける。
今回は、ピンバイスドリルで穴あけを行ったが、ルーター使った方が早そうです・・・

あとは、接着剤をつけて、開けた穴に入れればOK

ちなみに、接着剤はエポキシを使用。
パッケージにルアーが描いてあるので、間違いないでしょw

次は、コーティング作業へと続きます。
久しぶりにやっていると、やり方を忘れているところもあって、思い出しつつ、改善しつつやってます。
作業の方は、一通りの成形が終わり、次はパーツの取り付け。
ラインアイ、フックアイを取り付けるための穴を開ける。
今回は、ピンバイスドリルで穴あけを行ったが、ルーター使った方が早そうです・・・

あとは、接着剤をつけて、開けた穴に入れればOK

ちなみに、接着剤はエポキシを使用。
パッケージにルアーが描いてあるので、間違いないでしょw

次は、コーティング作業へと続きます。
2018年02月10日
フラットサイドクランク作成 その5
仕事から帰ってくると、家に入らず、そのまま作業場へ。
晩ご飯までの短い時間で、ちょっとずつ作業を進めてますw
さて、ナイフで角を落としたら、仕上げのサンドペーパー。
なめらかな曲線になるように、削っていく。

ナイフで削る作業も楽しいが、サンドペーパーでの作業も結構楽しかったりするw
ストーブで暖を取りながら、成形作業終了。

次は、ラインアイやフックアイ、ウエイトの取り付け作業です。
晩ご飯までの短い時間で、ちょっとずつ作業を進めてますw
さて、ナイフで角を落としたら、仕上げのサンドペーパー。
なめらかな曲線になるように、削っていく。

ナイフで削る作業も楽しいが、サンドペーパーでの作業も結構楽しかったりするw
ストーブで暖を取りながら、成形作業終了。

次は、ラインアイやフックアイ、ウエイトの取り付け作業です。
2018年02月09日
フラットサイドクランク作成 その4
忙しい毎日で、常にストレスフルな状態が続いている。
そんな中、絶対必要なのが気分転換。
そして、ものつくりに没頭するのは、自分にとって非常にいいストレス解消になる。
というわけで、フラットサイドクランク作成は、癒しの時間だったりするわけでw
さて、作業はいよいよ大好きな削りの段階へ。
ナイフを使って、角を落としていく。

今までは、最後の仕上げ以外はナイフで削っていたのだが、今回はサンドペーパーを多用する新工法を試すため、削る作業はこれで終了。

この新工法、できあがるクランクベイトはいいものになりそうですが、癒し効果は非常に低いですねw
そんな中、絶対必要なのが気分転換。
そして、ものつくりに没頭するのは、自分にとって非常にいいストレス解消になる。
というわけで、フラットサイドクランク作成は、癒しの時間だったりするわけでw
さて、作業はいよいよ大好きな削りの段階へ。
ナイフを使って、角を落としていく。

今までは、最後の仕上げ以外はナイフで削っていたのだが、今回はサンドペーパーを多用する新工法を試すため、削る作業はこれで終了。

この新工法、できあがるクランクベイトはいいものになりそうですが、癒し効果は非常に低いですねw
2018年02月08日
フラットサイドクランク作成 その3
連日、ちょっとずつ楽しみながら進めてみるクランクベイト作り。
一気に作ってしまいたい気持ちはあるものの、まとまった時間の確保はなかなか難しい。
さて、穴あけまで終わったところで、いよいよ大好きな削りの作業へ。
でも、この削りの作業がなかなか難しく、できあがってみると削る量のばらつきが非常に気になるところ・・・
できるだけばらつきができないように、工法の見直しをしてみることに。
面積の広いサイド部分をのテーパー状に削る部分は、特にばらつきが出やすい。
ナイフで削る方法だと、どうしてもうまくいかないのかも・・・
そこで、サンドペーパーを使って、均一に削る方法にチャレンジ。

ナイフで削る方法に比べると、かなり時間がかかる。
しかも、楽しさは激減・・・
でも、できあがりは明らかにいい感じ!

ここから先は、やっとナイフで削る作業へ。
とはいえ、サンドペーパーでの工法の良さに気づいたので、ナイフでの作業はちょっとだけになりそうです・・・
一気に作ってしまいたい気持ちはあるものの、まとまった時間の確保はなかなか難しい。
さて、穴あけまで終わったところで、いよいよ大好きな削りの作業へ。
でも、この削りの作業がなかなか難しく、できあがってみると削る量のばらつきが非常に気になるところ・・・
できるだけばらつきができないように、工法の見直しをしてみることに。
面積の広いサイド部分をのテーパー状に削る部分は、特にばらつきが出やすい。
ナイフで削る方法だと、どうしてもうまくいかないのかも・・・
そこで、サンドペーパーを使って、均一に削る方法にチャレンジ。

ナイフで削る方法に比べると、かなり時間がかかる。
しかも、楽しさは激減・・・
でも、できあがりは明らかにいい感じ!

ここから先は、やっとナイフで削る作業へ。
とはいえ、サンドペーパーでの工法の良さに気づいたので、ナイフでの作業はちょっとだけになりそうです・・・
2018年02月07日
フラットサイドクランク制作 その2
久しぶりにスイッチが入って、作り始めたクランクベイト。
現在、自分が作ってるのは、フラットサイドクランク。
以前は、バルサを使ったラウンドタイプのクランクベイトも作っていた。
でも、自分のよく行く野尻湖では、バルサのラウンドタイプより、フラットサイドの方が出しどころが多く、実際よく釣れる。
また、製法もフラットサイドの方が簡単だったりするw
前回、型を切り出したので、ウエイトを入れる穴をあけることに。
まずは、穴を開ける場所をマーキング。

そして、ドリルで穴あけ。
穴あけの作業自体は、非常に簡単なのだが、道具の精度が低いので、ちょっとコツがいる。

こうやって、ウエイトを入れる穴あけが終了。

そして、大好きな削る作業が待ってます!
現在、自分が作ってるのは、フラットサイドクランク。
以前は、バルサを使ったラウンドタイプのクランクベイトも作っていた。
でも、自分のよく行く野尻湖では、バルサのラウンドタイプより、フラットサイドの方が出しどころが多く、実際よく釣れる。
また、製法もフラットサイドの方が簡単だったりするw
前回、型を切り出したので、ウエイトを入れる穴をあけることに。
まずは、穴を開ける場所をマーキング。

そして、ドリルで穴あけ。
穴あけの作業自体は、非常に簡単なのだが、道具の精度が低いので、ちょっとコツがいる。

こうやって、ウエイトを入れる穴あけが終了。

そして、大好きな削る作業が待ってます!
2018年02月06日
フラットサイドクランク制作 その1
ずっと作ろうと思いつつ、なかなかスタートできなかったクランクベイト作り。
今回、行きたかった大会に参加できなかったことをきっかけに、スイッチが入り、久しぶりに作ってみることに。
今回作るのは、フラットサイドクランク。
スギ材で作っていたのだが、今回は初期に使用していたヒノキ材の在庫があったので、これを使って作ることに。
まずは、テンプレートを使って型を書く。

そして、糸のこぎりを使って切り抜く。

今回は10個ほど作る予定が、材料が少し余ったので、3個追加の13個切り抜いた。

久しぶりだったので、ちょっと時間がかかったものの、ここまで1時間足らず。
次は、ウエイトを入れるための穴を開ける作業です!
今回、行きたかった大会に参加できなかったことをきっかけに、スイッチが入り、久しぶりに作ってみることに。
今回作るのは、フラットサイドクランク。
スギ材で作っていたのだが、今回は初期に使用していたヒノキ材の在庫があったので、これを使って作ることに。
まずは、テンプレートを使って型を書く。

そして、糸のこぎりを使って切り抜く。

今回は10個ほど作る予定が、材料が少し余ったので、3個追加の13個切り抜いた。

久しぶりだったので、ちょっと時間がかかったものの、ここまで1時間足らず。
次は、ウエイトを入れるための穴を開ける作業です!